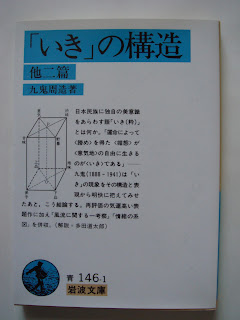 前回取り上げた岡倉天心と因縁のある九鬼周造の代表作です。1930年(昭和5年)岩波書店より出版。父親は九鬼水軍の末裔で明治の文部官僚を代表し、初代駐米公使を務めた九鬼隆一男爵。母親は星崎波津子(初子)。波津子は花柳界にいたとの説もあり、九鬼周造も学生時代から、東京の江戸花柳界で遊び、京都帝大教授時代の二番目の妻は祇園の芸妓の女性でした。天心と波津子の恋愛?が原因で九鬼と離婚後、天心との妻との確執の末、精神に異常をきたし、母親は非業の死を遂げます。そんな関係から、九鬼周造は幼少期の頃、自宅に来る天心を父親のように思っていたようです。そんな背景があり、日本民族にとっての独自の美意識をあらわす語「いき(粋)」とはなにかということを自身の体験から深く掘り下げることが出来たのかも知れません。
前回取り上げた岡倉天心と因縁のある九鬼周造の代表作です。1930年(昭和5年)岩波書店より出版。父親は九鬼水軍の末裔で明治の文部官僚を代表し、初代駐米公使を務めた九鬼隆一男爵。母親は星崎波津子(初子)。波津子は花柳界にいたとの説もあり、九鬼周造も学生時代から、東京の江戸花柳界で遊び、京都帝大教授時代の二番目の妻は祇園の芸妓の女性でした。天心と波津子の恋愛?が原因で九鬼と離婚後、天心との妻との確執の末、精神に異常をきたし、母親は非業の死を遂げます。そんな関係から、九鬼周造は幼少期の頃、自宅に来る天心を父親のように思っていたようです。そんな背景があり、日本民族にとっての独自の美意識をあらわす語「いき(粋)」とはなにかということを自身の体験から深く掘り下げることが出来たのかも知れません。日本の伝統風習文化が身近ではない北海道に生まれた私にとってはかなり難解な書籍でしたが、「いき」の芸術的表現にでてくる日本独自の微妙な色の呼び名の豊かさにあらためて驚きました。色の表現にしてから既に”いき”です。
そして、表紙にもある図解の説明には感心しました。
まずは直六面体の正方形をなす上下の両面を、底面を人生的一般性。上面を異性的特殊性と考え、八つの頂点に八つの趣味を置く。対角線によって結び付けられる趣味は相対立する一対になる。
上面は、渋み━甘み、野暮━意気。底面は、地味━派手、上品━下品。更にそれぞれの頂点を正方形の各辺によって結び付けられた頂点、意気━渋み、側面の矩形において対角線によって結び付けられる頂点、意気━派手、直六面体の側稜によって結び付けられた頂点、意気━上品、直六面体によって結び付けられた頂点、意気━下品等と常に何らかの対立を示していて、その対立の原理を対自性と対他性と捉え、対自性の対立は価値判断に基づくもの。対立者は有価値的と反価値的との対照。対他性の対立は価値とは無縁な物で対立者は積極性と消極性にわけることができると考える。
かなり混乱してきました!そして、底面の正方形の二つの対角線の交点をOとし、上面の正方形の二つの対角線をPとして、この二点を結びつける法線OPを引いてみる。
この相交わる直線が、意気━上品の矩形は有価値性を表し、野暮━下品の矩形は反価値性を表し、甘み━派手は積極性、渋み━地味の矩形は消極性を表す。
更に、そこから話が「さび」とはO、上品、地味のつくる三角形と、P、意気、渋みのつくる三角形とを両端面に有する三角柱。この三角柱の形こそが民族としての趣味上の最大の特色である。
「雅(みやび)」とは上品と地味と渋みとのつくる三角形を底面とし、Oを頂点とする四面体の中に存在する。
「味」とは甘みと意気と渋みとのつくる三角形で表す。
「乙(おつ)」とはこの同じ三角形を底面とし、下品を頂点とする四面体に位置するもの。
「気障(きざ)」は派手と下品とを結びつける直線状にあるもの…
なんだかこの図形は物凄い発見のように思われました。
九鬼周造は結論として、「いき」は武士道の理想主義と仏教の非現実性とに対して不離の肉体的関係に立っている。運命によって「諦め」を得た「媚態」が「意気地」の自由に生きるのが「いき」であると。
そして、人間の運命に対して曇らざる眼をもち、魂の自由に向かって悩ましい憧憬を懐く民族ならずして媚態をして「いき」の様態を取らしむることはできない。
ドイツ、フランスをはじめ8年間のヨーロッパでの勉学の末やはり興味の対象は日本の美と文化に惹かれていく結末は少し理解できそうな気がします。
※他にこの文庫には「風流に関する一考察」「情緒の系図」が収められています。


0 件のコメント:
コメントを投稿